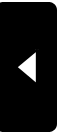2016年01月11日
111鏡開き111。

鏡開き。
ぜんざいを。
鏡餅には年神様が
宿っているといわれるから
割る、切るではなく
「開く」という
縁起の良い表現を使うそう。
関東と関西では、
「お汁粉」「ぜんざい」
呼び名が違うそう。
そう言えば、
沖縄で「ぜんざい」
かき氷に
金時豆を煮たのが
かかっていた!
今日のお昼は新年会。
こってり食べてか、
風邪か、、体調ダウン。
早めに休もう。
2016年01月07日
せりなずなごぎょうはこべらほとけのざすずなすずしろ。

今日は、七草。
子ども達が晴れ姿を
見せに来てくれた。
お着物姿が並ぶと
本当に艶やかで
美しかった✨

七草粥。
調べてみると
古い中国の習慣が
平安時代に日本に
伝わったそう。
1月7日の朝に
無病息災を願って
若菜を摘んで食べる習慣。
雪の下で芽吹く
若菜の生命力を
取り入れようとしたもの。
疾病予防と邪気払いの
おまじないとして普及し、
現在の「七草粥」となったそう。

今日は、初物!
空豆も頂いた。

今年も健康に過ごせますように✨
2015年12月27日
寒干し。

暖冬で寒干しが
どこも不作な様子。
干し柿も今年は
ダメだと聞く。
農家の方には
大変な年だったに
違いない。
私たちの畑も
雨と暖かさで
青虫が凄かった。
切り干し大根と干し芋は
作ろうかと考えて
いたけれど
この暖かさでは…と
様子を見ている。
出荷出来ないから…と
農家さんからお野菜を
頂くことが多かった。

漬け物用の大根も
農家さんから頂く。
子ども達がゴシゴシ。
仕事が終わってから
干場を見に出掛けてみた。

夕暮れ間近だったけれど
まだ、大根かけの作業を
されていた。


美味しく
干されますように☆
2015年12月22日
冬至にカボチャ…は何故なのか?

冬至に南瓜を食べる習わし
何故なのか気になって
調べてみた。
家でも母が毎年
冬至には南瓜を
煮てくれる。

おうち歳時記(成美堂出版)より。
インターネットにも
色々情報が載っていて
冬至には「ん」のつくものを
食べると縁起がよいとか。
かぼちゃを漢字で書くと
南瓜(なんきん)。
運盛りのひとつであり、
陰(北)から陽(南)へ向かうことを
意味しているらしい。
“冬至は「一陽来復」の日でもあり、
転じて悪いことばかり続いたあとでも、
ようやく幸運に向う日とされる”
とある。
柚子湯に入るのは、
寿命が長く病気にも強い
柚子の木にならって
柚子風呂に入って
無病息災を祈る風習。
実際ゆず湯は風邪予防にも
効果が高いらしい。
また、こんにゃくを食べると良い
という情報も至るところに
書かれてあった。
一年間たまった
砂下ろしをするためだとか。
どうやら、冬至とは
新しい年を迎える前に
運を呼びこむための
厄払いするための
禊(みそぎ)的な日らしい。

ただ1個
シワシワだけれど
柚子発見✨
今夜は柚子湯に浸かろう♪✨
続きを読む
2015年12月11日
はやとうり。

夕方、はやとうりを頂いた。
えいっ!と力を振り絞り
早速、漬け物にしてみた。

意外と簡単に出来た✨
あと二個残っている。
今回は醤油ベースにしてみた。
次回は、浅漬けに~♪
漬けたのを頂いたことはあったけれど
自分で作ったのは初めて。
皮を剥いてびっくり!!
ぬるぬるとも違うな……
きしきしとぬるぬるの中間。
手の指紋が無くなる感じ。
漬け物博士にメールしたら
「きゅうりといっしょで
パパインがあるんでしょう。
たんぱく質分解酵素」とお返事。
人生経験初の感触。
誰かと共有してみたい!
この感じ。
今、するする手がすべる。
不思議な感じ。
2015年11月14日
月暮らし

昨晩探し物をしていたら
同じ段ボールから出てきた子。

昔、親友が誕生日に贈ってくれた
土佐包丁。
大事になおしたままだったので、
使ってみることに。
りんご。
皮もむけるし、
カッティングも問題なし。
愛用していこう♪

探していたのは、こちら。
月好きが高じて随分前に購入した本。
見つかったはいいけれど、
難解なため就寝。。
思ったのは、
昔の人の暮らしは
月と密接していたということ。
私の住む海沿いの町の漁協。
大潮=満月の日はお休み。
びっくりした事実。
腕時計に、月齢の表示があるのを
最近になって船乗りさんから聞いて知る。
海の世界では、
月との暮らしが生きているんだろう。

今夜、月が見えたら
この中の魔法を試す予定。
(笑)怪しい?
2015年11月11日
芋いも芋いも、芋

農家さんから頂いたお芋。
子ども達と芋洗い。

紅あずまという品種。
ふかして、おやつに。

昨日頂いた焼き芋。
とーっても甘かった。
栗黄金という品種らしい。

こちらは黄金千貫。
焼酎の原料になるお芋。
水分が少なく繊維質が多い。
汁物に入れようかな。

祖父が育てた紫芋。
うちでは、大学芋に使う。
サツマイモ、調べてみると
店頭に出回るのが
およそ20種類くらいらしい。
↓旬の食材百科
http://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/vegitable/satumaimo-varie.htm
2015年11月10日
きのこ狩り!

「しいたけ採りに来ない?」と
梅干しの先生から連絡が入る!
仕事の気分転換もしたくて、
即、お返事。
「行く!」
指定された待ち合わせ場所から
車で舗装なしの傾斜を進む。

雨と暖かさが
重なり
シイタケ祭!

美しい。



山から降りる途中の景色。

どっさり。

今夜の食卓も
シイタケ祭♪
2015年11月04日
山ひとつ。

この姿を見て
前日の読売新聞のコラムを
思い出す。

今日は、祖父所有の山へ。

祖父は建設業を営んでいた。
材木が必要だったので
この杉山を購入したらしい。
海沿いに住む祖父は
他の市町村の山を。
それが、偶々、古民家の近く。
祖父の記憶を頼りに
車で道なき道を登る。
昔、小学生の頃に1度
こばれ=(下草払い)に同行した記憶が。
道なのか畑なのか分からない所を
くねくね登って
やっと辿り着いた。

見晴らしは最高!

薪を生産したいという気持ちと
どうやって木を切り出すのか…
課題がまたひとつ増えたような。
2015年11月03日
梅干しさん。

歴代の梅干し。
今年で梅干しを作り始めて
6年目になる。

歴代の梅干しを少しだけ
残して保存してある。
癌を患って
食べ物を何も受け付けなくなった人が
30年ものの梅干しなら口にでき、
20年ものでは駄目だった、
と聞いてから。
つわり期の友人達も
食べ物を受け付けないときは
結構な率で梅干しを頼りにしている。
梅干しは万能だと思う。
私も長い旅の時は必ず携帯している。
2年目の長老さん。

今年漬けた一番若手。

来年は申年。
申年の梅干しは貴重だと聞く。
多めに作ろうと考えている。

毎年、感染症に弱い私。
昨日から梅醤番茶を飲み始める。

極度の冷え性なので
今朝から、生姜生活もスタート。。
どうか健康で乗りきれますように、